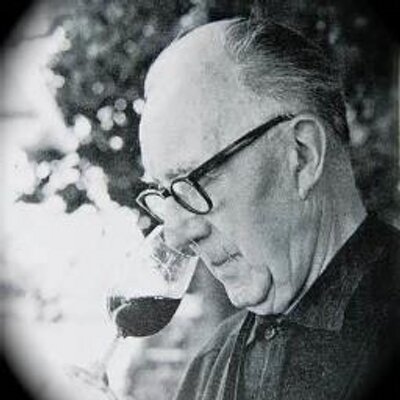Oct

MARCEL LAPIERRE 09 収穫現場レポート
マルセル 『自分が収穫した約40年間で生涯最高に素晴らしい葡萄の状態だった、』 とマルセルに言わしめた収穫だった。 2005年も記憶に残る素晴らしい年だった。 それを上回ることはないだろうと思っていた。 しかし今年はそれ以上のエクセプショネル・例外的な年となった。 私は収穫の初期と後半に3日間密着訪問した。 若者達が元気いっぱいによく働き、よく楽しむ、 この収穫期間はマルセルにとっても特別な日々だ。 収穫期間中は突発的な問題が次々と発生する。 プレス機が故障したり、各種機材が不足したり、人的トラブルであったり本当に続出する。 それらを何も無かったように解決して順調にことを運ぶのがマルセルの役割だ。今年はすべてがうまくいった。 満足そうだった。 47名で4チームの収穫グループを構成している。 それぞれの葡萄区画の熟度に合わせて収穫の順序決定していく。 過酷な労働の後の楽しい夕食と団欒のひと時 マルセルには1チームはプロ中のプロ軍団がいる。 普通の収穫人が一人300KG/日収穫するところを 800KG/日のスピードでしかも確実に良い葡萄だけを選果しながら行ってしまうポペット軍団と呼んでいる。 後は学生や若者を中心にした3チームだ。 朝、昼、晩食を共に過ごす合宿生活が約3週間続く。 朝、7時に共に朝食をとり、7時30分から12時30まで、昼食後13時:30から17:30まで収穫が続く。 仕事は体力的に実にキツイ仕事だ。 夕食と夕食後のひと時は歌ったり、踊ったりの楽しい時間を共にする。 収穫メンバーにはプロ級のミュージシャンがいる。 このひと時がなかったらやっていられない。 そして、この収穫で知り合ってカップルが毎年出来上がる。 実はマルセル自身も奥さんのマリーさんが収穫に来て知り合い結婚したのである。 大自然の中厳しい仕事を一緒にして、朝、昼、夜を共にすると情も伝わるものだ。 収穫―運搬―冷房(冷やし)-アル発酵―マセラッション(かもし)-プレスー最終アル発酵 収穫人は各自大バケツを持ちながら収穫した葡萄をバケツに入れいく。 一杯になると畑に設置してある小型プラスチック箱に移しかえる。 そして、そのケースを醸造所まで運んでいく。 温度が高い場合は、冷蔵庫に一晩冷やしておく。 大型の冷蔵トラックが醸造所に設置されている。 そして、翌日、除梗せず房ごとトロンコニック型の木樽発酵槽に入れられる。 セミ・マセラッションカルボニック方式で発酵させる。 発酵途中、つまりまだ残糖が残っている段階でプレスにかける。 半ワイン・ジュースをさらに発酵槽に戻しアル発酵を継続させる。 キュヴェーゾン(かもし)の期間は造ろうとするワインのスタイルによって違う。 娘カミーユがプレスを担当 2009年はマルセルの娘カミーユがプレス作業を担当。 カミーユは次々と運ばれてくる葡萄をチェックして糖度を測って記録する担当でもある。 木製のプレス機2台をフル回転で行っている。 ゆっくり時間をかけてやる作業である。 カミーユはソムリエでもあり、夏はビアリッツのレストランでソムリエとして研修をした。 長男のマチュは葡萄園から醸造所までブドウ運搬をしながら全体の流れを管理。 マチュは05、06、07、08、09と5年目の収穫だ。 既にマルセルが40年間で経験した最良の年と最悪の年を経験したことになる。なぜなら07、08の2年間は雨、雷・雹、湿気、ベト病と最悪の年だった。 05、09は例外的な最良の年だった。 身をもって後継者にやるべきことを共有しながら教えられたことはマルセルは大満足だ。 マチュにとっては掛け替えのない経験となった。 マリーさんは収穫現場の隊長だ!収穫人の葡萄園から葡萄園の移動や収穫状況をチェック 収穫人が葡萄園を移動する時はマルセルも駆けつけて、 収穫状況をチェックして、みんなを元気付ける。 2009年エクセプショナル・特別な収穫終了の雄叫び!! まるでジャンヌダルクのようだ! 厳しい仕事をやり遂げた、喜びだ!! マルセル・ラピエ-ル の ヌ-ヴォーには 彼らのエネルギーが 入っている!! Marcel Lapierreのワインの情報は、こちらまで: 野村ユニソン株式会社 TEL : 03-3538-7854 FAX : 03-3538-7855 MAIL : wine@nomura-g.co.jp http://www.nomura-g.co.jp